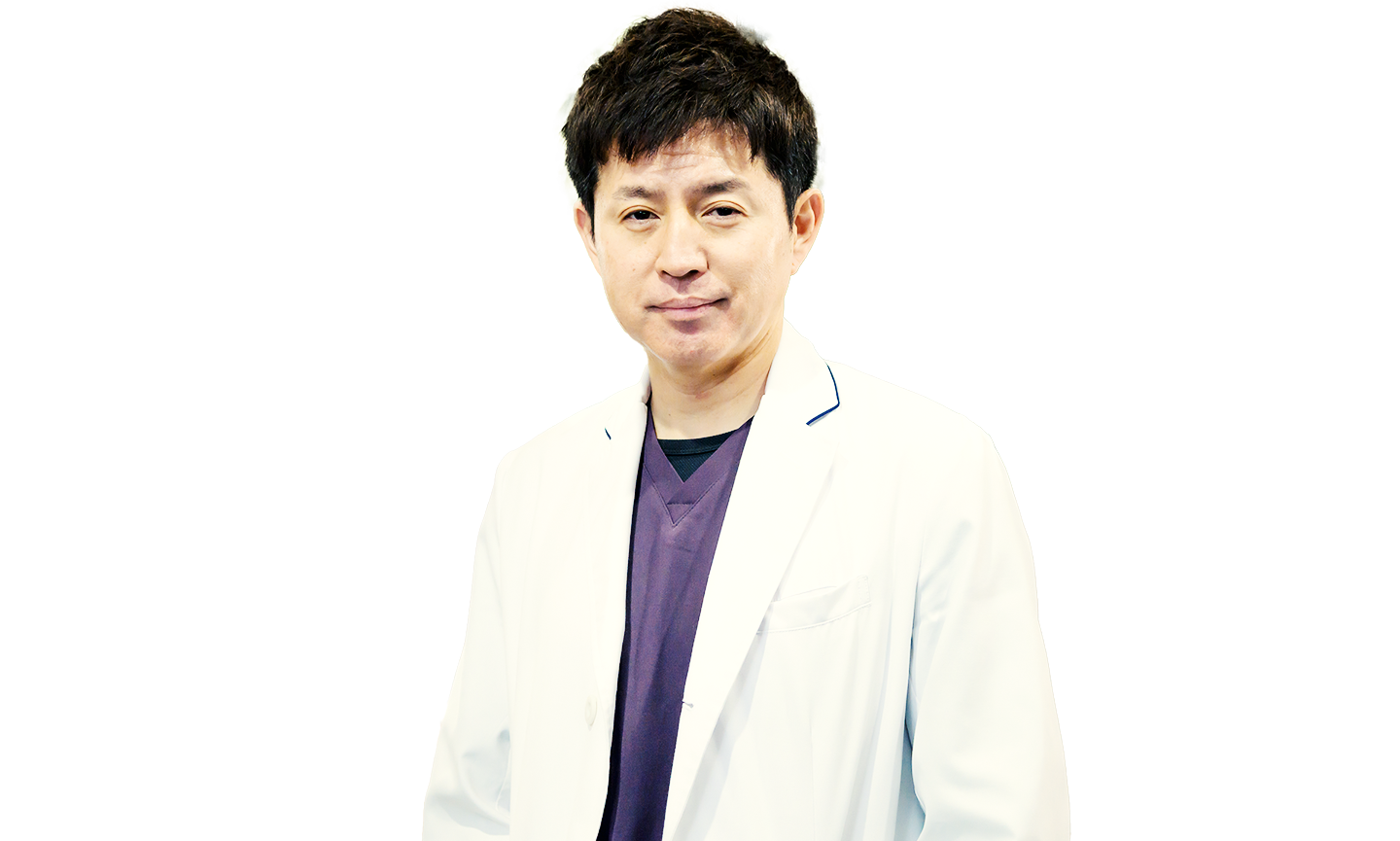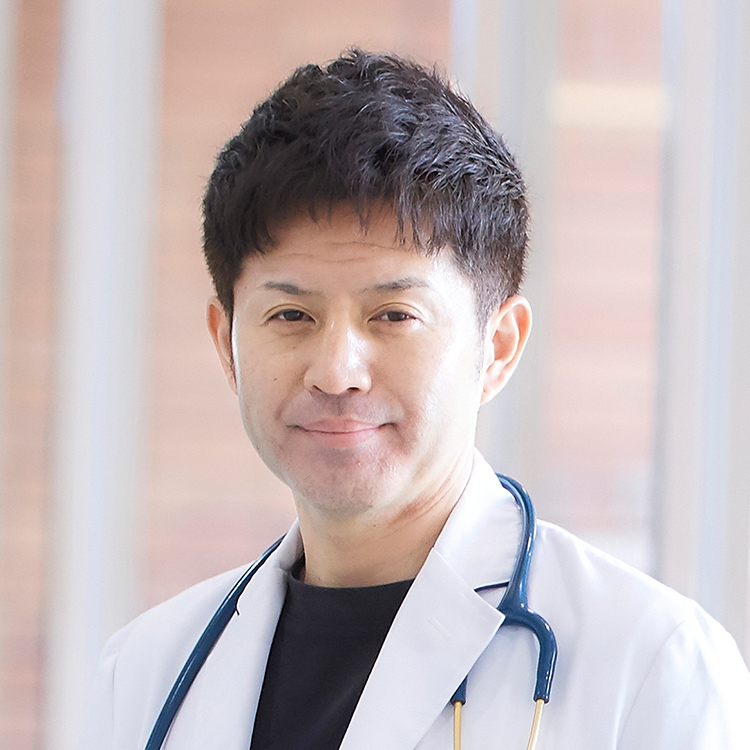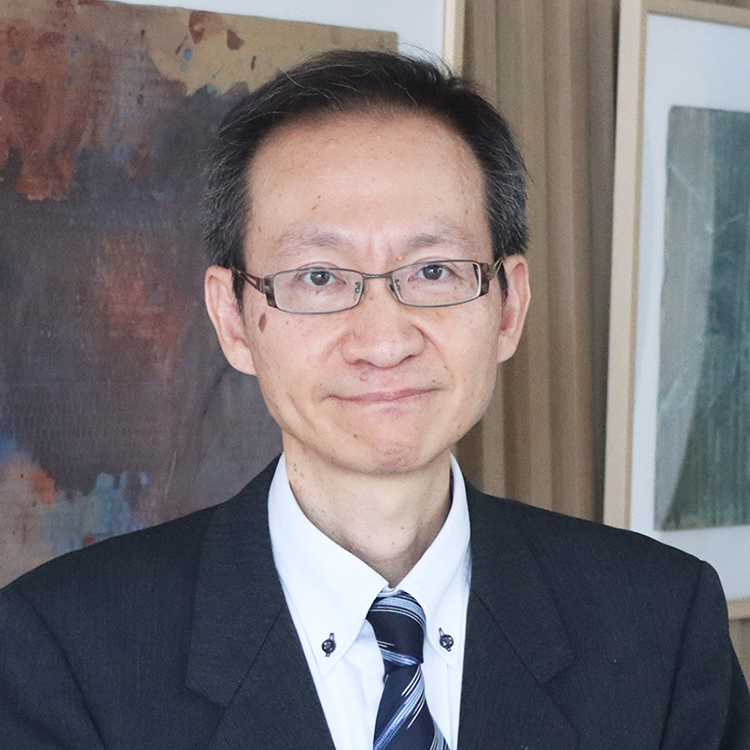幅広い知識と技術を持つ
時代が求める言語聴覚士に。
HEARING THERAPY MAJOR
保健医療学部
総合リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻
総合リハビリテーション学科
4 YEARS OF LEARNING
4年間の学び
1年次
言語聴覚学の基礎知識を身につける
言語聴覚学の基本概念、言語聴覚障害の種類やその症状、言語聴覚士の仕事内容の基礎知識について具体例を通して学びます。さらに言語のしくみを理解するための言語学や、人の言葉や発声に関連する心理学系、基礎医学系の科目を学び、専門的な学修への基礎を固めます。また、小児施設や高齢者施設での見学実習も行います。1年から言語聴覚臨床に直接触れる見学実習を行います。
2年次
専門知識・技術を学ぶ
講義・演習を通して、コミュニケーション障害の症状を専門的に分析する能力を養います。言語聴覚士には言語と聞こえの障害をもたらす様々な病気、脳や発声・発語器官の働きについての深い知識が求められます。コミュニケーション障害の発生メカニズムを理解し、それを正確に評価・診断する技術も必要です。2年次では各種の言語聴覚障害の特徴を把握し、専門的に分析する方法や手順を習得すると同時に、医学領域の知識も学びます。この年次で評価実習を行います。
3年次
病院や施設での臨床実習で専門的技術を習得
障害ごとの原因・症状・評価法・治療を知る専門科目を多数開講します。専門科目において、失語症、言語発達の遅れ、発声・発語の障害、吃音、難聴、飲み込みの障害など言語聴覚障害の原因・症状・評価・治療法について深く掘り下げます。専門科目の学習を裏付けるために評価を主体とした臨床実習を実施します。
4年次
臨床で活きる実践力・思考力を身につける
「卒業研究」「卒業論文」の科目では、研究論文を読み解き、主体的な研究能力を身につけます。そして、1年を通して、一歩一歩言語聴覚士の国家試験に向けての学修を固めていきます。8月以降は就職活動も行います。
CURRICULUM
時間割例
(2年前期)
| MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運動性発声発語障害学 | 社会保障制度 | 言語発達障害学 | 聴覚障害学 | |
| 2 | 摂食・嚥下障害学 | 臨床心理学 | 失語症学 | ||
| 3 | 精神医学 | 内科学 | 器質・機能性発声発語障害学 | ||
| 4 | 基礎セミナーⅡ | 小児科学 | 病理学 | ||
| 5 |
- 開講科目、時間割は変更になる可能性があります。
INTERNSHIP
主な実習先
- 医誠会国際総合病院
- 大阪医科薬科大学病院
- 関西医科大学病院
- 堺市立総合医療センター
- 関西リハビリテーション病院
- 千里リハビリテーション病院
- 明生病院
- 大阪赤十字病院
- 富永病院
- 豊中平成病院
- 甲南医療センター
- 西宮協立リハビリテーション病院
- 国立病院機構近畿グループ 兵庫中央病院
- ことばの道
- 広畑センチュリー病院
- みなとのこども診療所
- 奈良県総合医療センター
- 奈良東病院
- 発達支援教育センター アミークス
- こども発達支援MOMOの実
- よつばCOLORS
- 宇治リハビリテーション病院
- 京都大原記念病院
- 洛和会音羽病院
- 滋賀医科大学医学部附属病院
- 済生会守山市民病院
- 琵琶湖中央リハビリテーション病院
- 和歌山県立医科大学附属病院
- 愛徳医療福祉センター
- 和歌山医療センタ
など多数
SPECIALIST
各分野のスペシャリストがあなたを導きます。
研究者の特集記事をご覧ください。
VOICE
先輩VOICE
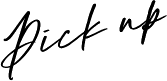

印象に残っているのは、喉の理解のために紙で模型を作ったこと。
総合リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2年
私立初芝富田林高等学校出身
私は高校生の時に参加した病院見学がきっかけで、言語聴覚士という職業を知りました。実際の言語聴覚士の姿を見て、私も生活に支障があり困っている患者さんの暮らしに寄り添いたいと思うようになりました。講義では『発声発語系医学』という人体の喉の解剖や動きについて学ぶ講義が印象に残っています。喉の解剖を理解するために紙で喉の模型を作りました。実際に自分たちで模型を作ったため、記憶に定着しやすく、より理解を深めることができました。言語聴覚士はこれからもっと社会から求められる仕事です。絶対に夢を叶えます。
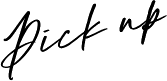

国家試験の合格率が高く、
病院実習が充実しています。
総合リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2年
私立仁愛女子高等学校出身
国家試験の合格率が高く、病院実習などが充実しており実践力が身につく点に惹かれ、大和大学に進学を決めました。1年次から実際の病院の見学実習を経験したおかげで自身の知識不足を痛感し、学習に対するモチベーションアップにつながりました。また、言語聴覚士の仕事を間近で拝見させていただいたことで、自分が目指す言語聴覚士のビジョンが鮮明になりました。専門知識はもちろんですが、コミュニケーションを大切にしながら、患者さま一人ひとりの心に深く寄り添う言語聴覚士になりたいです。
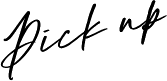

人に伝えることは難しいですが、
全ての人に自分の言葉を伝えてほしい。
総合リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 4年
大阪府立三島高等学校出身
小さい頃から人の言葉に敏感でした。すぐに傷ついたり、反対にちょっとした言葉で元気になったりしました。私自身言いたいことがうまく伝わらないことがあります。コミュニケーション障害をお持ちの方々はもっと苦労しているだろうと思い、その手助けができたらと進学しました。学ぶうちに、言葉選びや伝え方、コミュニケーションの取り方が変わってきました。やりたいこと見つけるのは難しいですが、将来なりたい人をイメージするのも良いと思います。言語聴覚士は、素敵な職業ですよ。
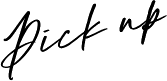

人生の手助けができる
言語聴覚士に成長したい。
総合リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 4年
兵庫県立西宮高等学校出身
高校生の頃は漠然と、誰かの記憶に残る職業に就きたいと思っていました。オープンキャンパスに参加するまでは、「言語聴覚士」という職業さえ知りませんでした。入学して専攻の先生方との出会いを通じて、この職業を選んで良かった!ますます深く学びたい!と思いました。将来は患者さんの思いに寄り添い人生の手助けができる、記憶に残るような言語聴覚士になりたいです。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME