

「観光×防災」の情報提供を通して、
訪日外国人に楽しみと安全を提供
「観光×防災」の情報提供を通して、
訪日外国人に楽しみと安全を提供
佐々木 淳教授


訪日外国人向け
観光・防災ポータルサイトについての研究
長年、オーバーツーリズムの解決の一助となり、地域活性化にもつながる観光推薦システムや旅行計画データベースの研究を手がけてきた佐々木教授。現在は、生成AIを取り入れた観光プランの構築や、防災情報の発信に関する研究に力を注いでいます。訪日外国人の旅行者数が過去最高を更新し続けるなか、時代のニーズに合った研究を進めているところ。最終的なゴールは、訪日外国人向けの観光・防災ポータルサイトを完成させることです。

生成AIを駆使し、
一人ひとりのニーズに合った旅行プランを作成
日本政府観光局(JNTO)の調査によると、2024年7月の訪日外国人旅行者数は329万2,500人。2ヵ月連続で、単月の過去最高を更新しました。人気観光地に旅行者が殺到し、地域の方々の暮らしに悪影響を与えるオーバーツーリズムが社会問題化。そんななか、観光客を分散させ、“観光公害”解決の一助となる研究を手がけているのが佐々木教授です。
「日本には、知名度が低いものの、魅力的な観光資源を有した地域がたくさんあります。東日本大震災で被災した東北の三陸沿岸地域もそのひとつ。豊かな観光資源や食文化があるにもかかわらず、観光産業は低迷し、いまだに復興が進んでいません。そこで、観光客を分散させ、有名観光地への一極集中からの脱却を図るために、独自の観光推薦システムを立ち上げました」
佐々木教授が手がけたのは、季節や日数、予算などを入力するだけで、その方に合った旅行プランを紹介するというシステム。プランを考案したのは学生たちで、すでに70以上のコースが用意されており、『旅行計画データベース』として多言語対応で一般公開されています。
「これまで観光旅行を計画する際には、観光地の選び方や交通手段、宿泊場所の決定に多くの時間や手間がかかっていました。そこで、本研究では満足度の高い旅行プランを複数作成し、それをデータベース化。ユーザーが希望に合ったプランを簡単に探せるようにすることで、手軽に観光旅行の計画が立てられる仕組みを構築しました」


現在、佐々木教授は生成AIを活用した旅行計画作成システムの研究にも注力。「旅行計画を生成AIでつくってみたい」という学生のアイデアに耳を傾け、実現に向けてチャレンジしているところです。
「学生が卒業研究時に活用できるよう、今は生成AIに的確な指示を与えるプロンプトを工夫するなど、試行錯誤を続けています。観光推薦システムに生成AIを組み合わせることができれば、旅行者の漠然とした要望やよりきめ細かなニーズに対応できるようになるでしょう」
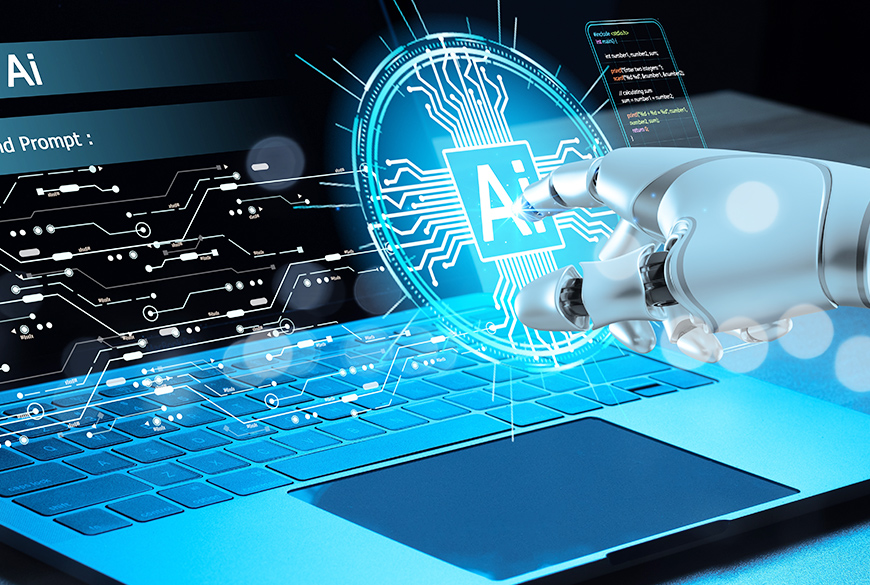

防災ポータルサイトの構築を通して、
訪日外国人の防災意識を高める
2024年8月、政府は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を初めて発表しました。何をどうすればいいのかわからず、戸惑いを覚えた方も多いでしょう。そんななか、地震に慣れていない訪日外国人は、日本人以上に混乱したとニュースでも報じられました。
「地震や台風が多い日本で生まれ育った私たちと違い、外国人の多くは自然災害に対する知識があまりありません。避難所に対して“空襲を避ける防空壕のようなシェルター”をイメージしている外国人もいるくらいです。そこで、観光推薦システムの研究と合わせて、訪日外国人向けの防災ポータルサイトの研究もスタートさせました」
訪日外国人は、ただでさえ災害に備えるための知識がじゅうぶんではありません。さらに、言葉の壁や習慣・文化の違いから、地震や台風に遭遇した場合、パニックに陥る危険性があります。
「旅行前に日本に関する防災知識を得られる防災ポータルサイトがあれば、万が一のときでも慌てずスムーズに対応できるはず。そこで、防災に関する基礎知識を身につけ、防災関連のアプリをインストールしてから旅行に来てもらえるようなスキームを構築したいと考えています。同時に、日本のマナーや交通標識の知識、そのほかの留意事項をまとめて情報を発信。観光推薦システムと連携させることで、“旅行×防災”をワンセットでとらえることができるようになるでしょう」


2013年、佐々木教授は他大学の教授たちと防災に特化した国際会議「ITDRR」をブルガリアで立ち上げました。以来、毎年1回グローバル規模で、防災に関連した情報や技術に関する意見交換を行っています。
「私が防災に興味を持ったきっかけは、東日本大震災です。当時、岩手県立大学に在籍しており、復興支援活動にも携わりました。
そんななか、防災情報関連の研究をしている欧州の大学教授に誘われて、世界でも珍しい国際会議を立ち上げることになったのです。海外に目を向けることで、日本と外国の防災に対する考え方の違いを理解することができました。訪日外国人向けの防災ポータルサイトの研究を進めるうえで、この会議は大変役立っています」


ICTを用いて、地域の課題を
解決できる人材へと成長できる
旅行に関するこれまでの研究は、単に魅力度の高い観光地を推薦するものが主流でした。しかし、佐々木教授の研究は観光地の魅力に注目するだけでなく、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンス、災害や事故のリスクなども考慮している点が特徴。そこが、この研究のおもしろさにつながっているそうです。
「知名度の低い観光地にスポットライトを当て、新しい観光資源を見つけたり、被災地の復興を支援したりする点においても、とても価値のある研究だと自負しています。生成AIを駆使し、旅行に関するさまざまなニーズ(人数・季節・日程・旅行先・予算など)を入力するだけで、一人ひとりに適した旅行計画や旅行先の防災・事故に関する留意事項がまとめて表示されるシステムを構築することが、この研究のゴールだと言えるでしょう」
観光と防災をテーマにした佐々木教授の研究は、学生たちにとっても非常に身近な内容です。そのため、楽しみながら学びを深めていくことができるでしょう。
「自分が知らなかった地域の魅力に触れられるのが、大きな特徴です。また、Webシステムやデータベースの構築など、IT人材として必要なスキルを伸ばすことができ、ICTを用いて地域の課題を解決する力を手に入れられるのもポイント。研究の成果を一般の方々が見ることができるWebシステムとして具現化できるので、大きなやりがいを感じられると思います」


佐々木教授のモチベーションの源は、学生たちの成長だそう。そのための労力は惜しまず、チャレンジの場を提供しています。
「つい先日は、生成AIに関する高いスキルを有する2年生の学生を連れて、ある学会に参加。『生成AIを用いた旅行計画作成方法に関する一検討』というテーマで、大勢の前で発表をしてもらいました。2年生で学会発表をした経験は、大きな自信や成長につながるでしょう。また、リモートで東日本大震災の被災地の高齢者にデジタルスキルを教える『i-MgNT(愛のマゴの手)プロジェクト』を展開。参加した学生たちは、コミュニケーションスキルを磨きながら頑張っています。大和大学はまだまだ歴史が浅い大学なので、新しいチャレンジは大学の歴史に刻まれるはず。フロンティア精神を大切にしながら、一緒に新しい道を切り開いていきましょう」




佐々木 淳 教授
岩手大学工学研究科電気工学専攻修了。大手通信会社に就職し、光ファイバー関連の研究・開発などに携わる。在職中に論文審査で博士号を取得。1998年に退職し、岩手県立大学が開校されたタイミングで助教授に。准教授、教授、特命教授を経て、2023年に大和大学へ。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME