

楕円曲線の有理点の構造を解明し、
誰もなし得ていない発見に挑む
楕円曲線の有理点の構造を解明し、
誰もなし得ていない発見に挑む
吉田 学講師


y²=x³+ax+bという形のなめらかな
楕円曲線の有理点の構造を解明
数の世界を広げたときに素数がどのように分解されるか、その法則性を解明する研究を行っている吉田講師。特に、楕円曲線という数学上の重要な対象の有理点の構造を調べ、その性質や大きさを明らかにしようとしています。楕円曲線はフェルマーの最終定理の証明や暗号理論にも応用されているもの。吉田講師は数値実験を通して新たな発見を目指し、「存在しないことの証明」という難問に挑み続けています。

楕円曲線の性質を利用して
証明されたフェルマーの最終定理
吉田講師は、素数が数の世界を広げるとどう変わるのかを研究しています。通常、私たちが知っている「素数」は、1とその数自身でしか割り切れない数(例えば2, 3, 5, 7…)ですが、虚数(例えば√-1のこと)を含む新しい数の世界では、これまでの素数が別の数に分解できてしまうことがあります。
「例えば、2=(1+i)(1-i) 、5=(2+i)(2-i)というように、虚数を含めた世界では2,5はさらに分解できるのです。いっぽう、3, 7, 11は素数のまま。このように、数の世界を広げたときに、どの素数が分解できるのか、そこにどんな法則があるのかを解き明かそうとしています。この研究は数の性質の奥深さを知る手がかりであると同時に、数学の基礎を支える重要なテーマだと言えるでしょう」
現在、吉田講師が力を注いでいるのは、楕円曲線の有理点の構造を調べること。楕円曲線とは、y²=x³+ax+bという形のなめらかな曲線のことで、数学のさまざまな分野で登場する重要な対象です。
「この楕円曲線の上では、点と点を足し合わせる特別なルールを決めることができます。数の足し算と同じように、曲線上の2つの点を足し合わせて新しい点を求めることが可能。そして、有理数の座標を持つ点の集まりを『Mordell-Weil群(モーデル・ヴェイユ群)』と呼びます。この群の大きさや性質については未解明の部分が多く、現在も世界中の数学者たちが研究を続けています」


この楕円曲線は応用範囲も非常に広く、例えば数学の難問の解決にも利用されています。特に有名なのが、かつて誰も証明できず数学界最大の難問とも呼ばれたフェルマーの最終定理。この定理も、楕円曲線の性質を利用して証明されました。
「また、暗号理論にも実は楕円曲線が活用されています。楕円曲線上の点には特別な足し算のルールがあり、この計算を使うことで非常に安全な暗号の仕組みをつくることができるのです」


世界でまだ誰も知らないことを、いち早く知りたい
吉田講師の研究の目的は、数の範囲を広げたときに楕円曲線の『Mordell-Weil群』の構造がどのように変わるかを明らかにすること。これは楕円曲線の持つ複雑な数学的性質の一部を解明するものであり、そのなかには「計算の難しさ」という特徴も含まれます。
「この計算の難しさにより、楕円曲線は情報通信の分野で暗号の安全性を支える重要な要素として応用されています。私たちが普段使っているスマートフォンやパソコンは、楕円曲線を用いた暗号によって安全性が守られているのです。また、電子マネーやネットバンキングなどのサービスの舞台裏でも、楕円曲線を用いた暗号技術が重要な役割を果たしていると言えるでしょう」
楕円曲線の研究のおもしろさについて、吉田講師は「計算機を使って数値実験ができること」だと教えてくれました。手で計算するのが難しい複雑な問題も、計算機を使えば知りたいデータを正確に得られるそうです。
「計算機を使って計算しながら、新しい定理が成り立つかどうかを予想したりするのですが、想定とはまったく違う結果が出て驚くことも多数。そうした意外な発見も、研究のおもしろさにつながっています」


吉田講師の原動力は、「世界でまだ誰も知らないことをいち早く知りたい」という強い想いにあります。この好奇心と探究心が、難解な問題にも挑み続ける力となっているそうです。
「フェルマーの最終定理のように、特別な性質を持つ楕円曲線が存在しないことを証明するのが、大きな目標のひとつです。数学では、『あるものが存在する』と確かめることよりも、『存在しない』と証明するほうが難しい場合があります。これも数学のおもしろいところだと言えるでしょう。特別な性質を持つ楕円曲線が存在しないことを証明するのは簡単ではありません。しかし、そこにたどり着ければ大きな発見となるため、高いモチベーションで挑み続けることができます」


数学に真摯に向き合う姿勢を養うため、
数学の本を読み込むゼミを開講
吉田講師によると、大学の数学は高校の数学と比べて非常に難解なのだそうです。「高校で数学が得意だったから」という理由で進学し、挫折を経験する学生が多いのだとか。特に、大学の数学は証明が中心となるため、面食らう学生が多いとのことです。
「大学の数学は、地道に一歩ずつ理解を積み重ねていくことが大切です。だからこそ、ゼミではみんなで一冊の本を読み、インプットしたことを発表してもらうという取り組みを行っています。文章の行間をしっかり読み取って理解しなければ、本当の意味で内容をつかむことはできません。そのため、ただ文字を追うだけでなく、考えを深めて疑問を持ちながら読み進めることが重要です。そうすることで、数学に真摯に向き合う姿勢が自然と身につくでしょう」
楕円曲線の研究には、代数学の理論だけでなく、幾何学のテクニックも欠かせません。また、L関数という解析的な対象とも関わりがあり、さまざまな分野とのつながりを通して、数学に対する広い視野を養うことができるそうです。
「さらに、暗号理論に代表されるように、数学が私たちの実生活でどのように活用されているかを実感できるのも、この研究の魅力だと言えるでしょう。以前、学生たちに暗号を解読する課題を出したところ、パソコンの計算ソフトを駆使しながら、みんな楽しそうに取り組んでいました」
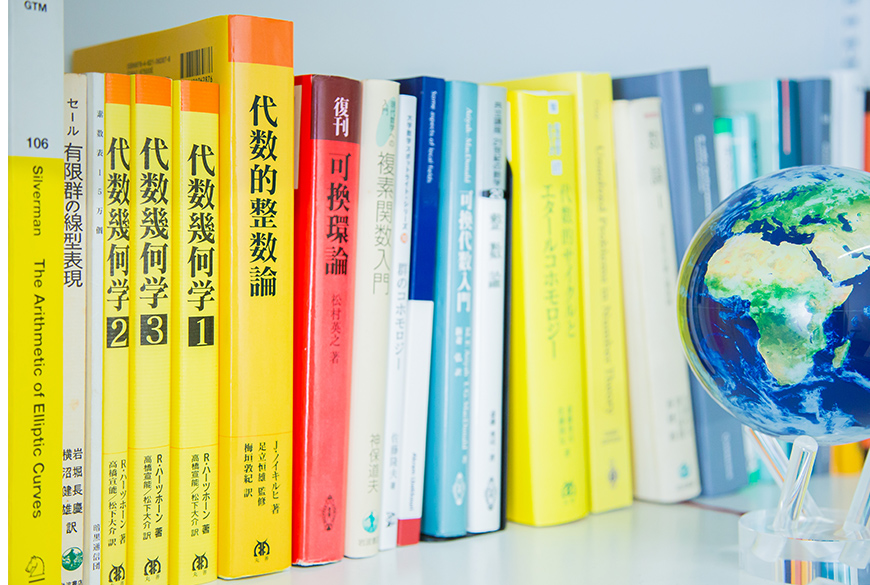
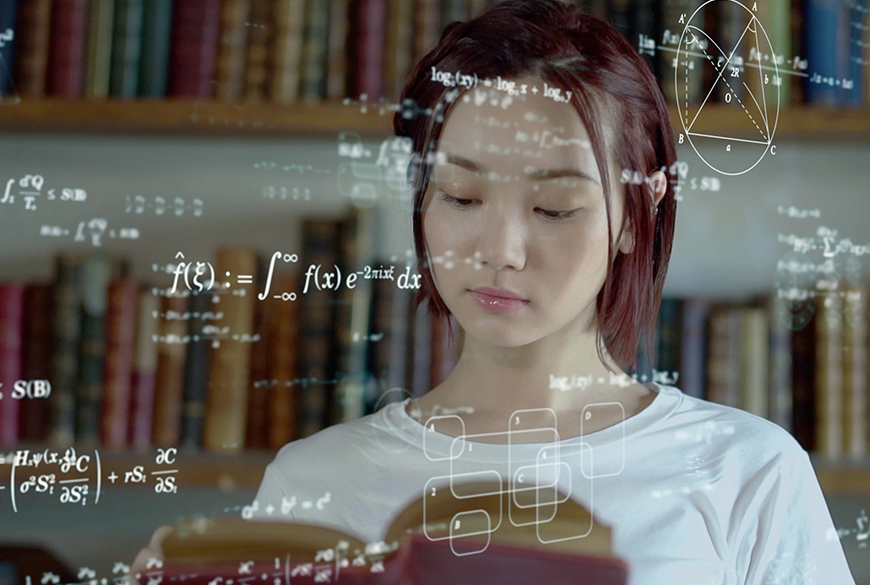
「楽しい」という気持ちは、成長の最大の原動力になります。何かを学んだり、新しいことに挑戦したりするうえで、「楽しい」と感じる瞬間ほど、人を前向きにさせるものはありません。
「人は楽しいことなら、自分の頭で考え、主体的に動きたくなるものです。『おもしろそう』『もっと知りたい』と感じた瞬間に、自ら方法を調べ、工夫し、挑戦し始めます。そうなれば、自然と学びの質も深まり、自分自身の力としてしっかり身についていくでしょう。皆さんには、知的好奇心や探究心を大切にしながら、数学の世界を極めてほしいと思っています」




吉田 学 講師
福岡教育大学教育学部初等教育教員養成課程自然コース を卒業後、九州大学大学院数理学府の修士・博士課程へ。その後、九州産業大学付属九州産業高等学校の常勤講師や教諭、富山高等専門学校の講師として活躍。2024年に大和大学に着任し、数学教育や研究に力を注いでいる。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME