

人間の高次脳機能の解明を目指し、
高次脳機能障害の作業療法の可能性を追求
人間の高次脳機能の解明を目指し、
高次脳機能障害の作業療法の可能性を追求
福本 倫之教授


高次脳機能が人間の動作や行動に与える影響と高次脳機能障害の作業療法について
記憶、注意、遂行、言語などの能力を統合し、人間の高度な思考や行動を支える高次脳機能。福本教授は、この機能が人々の日常生活のさまざまな動作や行動にどのような影響を与えるのかについて研究しています。また、高次脳機能や作業能力を向上させる効果的な方法を見つけることにも注力。こうした研究を通じて、リハビリテーションの目標である“全人的復権”や、作業療法が目指す“その人らしく生き生きと”を実現したいと考えています。

高次脳機能は、
人間が人間らしく生きるために欠かせない機能
作業療法士として病院で身体障害者のサポートにあたっていた頃に、高次脳機能障害に出会った福本教授。それをきっかけに、「高次脳機能障害をもっと知りたい」という想いが芽生え、臨床の現場から研究の道へ進むことを決意しました。高次脳機能障害とは、考えたり、覚えたり、行動をコントロールしたりする力が上手く働かなくなる状態のこと。交通事故や病気などによる脳のダメージが原因で、引き起こされる障害です。
「人間の脳は、運動や感覚に関する情報を処理して身体をコントロールするだけでなく、より高度な機能を備えています。注意機能、記憶機能、言語機能、遂行機能などが、その一例。これらの高次脳機能は、人間が人間らしく生きるために欠かせない機能です」
高次脳機能障害になると、こうした重要な機能が失われ、社会生活を送るうえでさまざまな困難が生じることがあります。
「障害のあらわれ方は人それぞれですが、例えば物事に集中できなくなったり、記憶力が低下して物を覚えられなくなったりすることがあります。また、言葉が上手く話せなくなるケースも少なくありません。そのほか、計画を立てて予定通りに物事を進めることが難しくなることもあるでしょう」

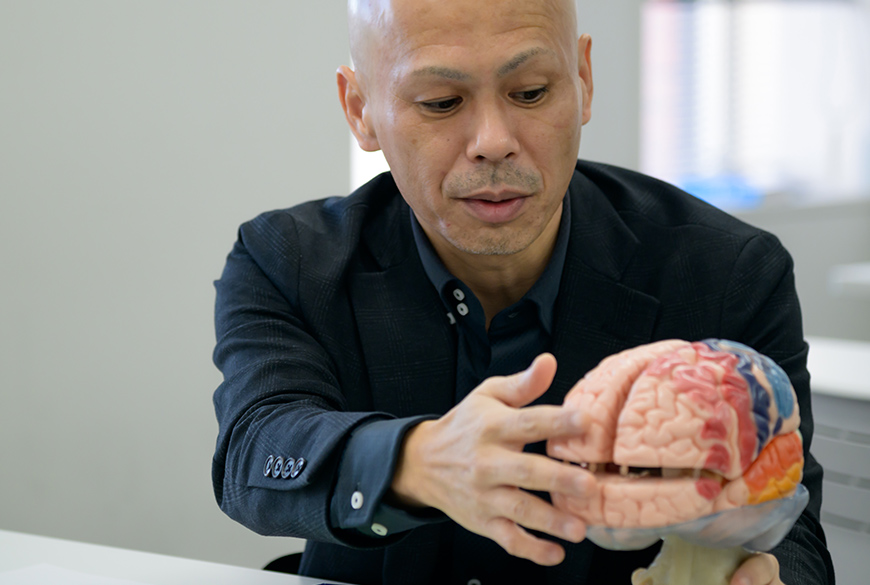
人間の脳の働き、特に高次脳機能が日常生活の動作や行動にどのような影響を与えるかについて研究を行っている福本教授。また、高次脳機能や作業能力を向上させる、効果的な方法の発見にも取り組んでいます。
「私のミッションは、注意や記憶といった高次脳機能や、それに関連する障害が人々の暮らしにどのような影響を与えるのかを明らかにすることです。この研究は、“人間らしさ”や“生活の質”の向上に直結するため、大きなやりがいを感じています」


高次脳機能と人間の動作や行動の関係を、
ひとつでも多く明らかにしたい
福本教授は現在、高次脳機能に関するさまざまな実験を行っています。注意機能の実験では、健常者に革細工にチャレンジしてもらい、制作の過程でどれくらい注意を保てれば上手く完成にこぎつけるかを調査。また、本を見ながら文字を抜き出してパソコンに入力してもらい、どれくらい時間が経てばタイピングのミスが増えるのかを調べる実験を行ったこともあるそうです。
「注意機能と一言で言っても、集中力の持続性や物を選り分ける選択性など、さまざまな特性があります。こういった実験を通して、生活のなかでどのようなシーンに、注意機能のどの特性が必要なのかを明らかにしたいと考えているのです」
福本教授によると、この研究の魅力は日常生活すべてが研究対象になることだといいます。また、人間の脳はまだまだ未知数な部分が多いとか。そこが難しさでもあり、同時におもしろさにもつながっているとのことです。
「人が生活するなかで行う作業は、無限に存在します。高次脳機能とそれらの関係を、ひとつでも多く明らかにすることが目標。また、人が生きていくうえで、単に身体が動くだけでは、自分らしい生き方はできません。その人らしさを発揮するためには、高次脳機能が不可欠です。だからこそ、研究結果を脳損傷患者さんのリハビリテーションや作業療法に応用し、実際の現場で役立てたい。この研究が、リハビリテーションの目的である“全人的復権“や、作業療法の目的である“その人らしく生き生きと”に直結している点に、大きなやりがいを感じています」


自分たちの暮らしに身近な内容だからこそ、福本教授の研究を通して学生たちは多くの学びを得ることができます。
「日々の生活のなかで、人は目的を持ってさまざまな行動を取っています。例えば、歩くこと自体は手段であり、目的ではないですよね。『トイレに行くため』や『大学へ行って勉強するため』、または『コンビニへ飲み物を買いに行くため』といった目的があるから歩くのです。目的を達成するためには、身体の動きだけでなく、高次脳機能という脳の働きも重要であることを、この研究を通して再認識できるでしょう」


作業療法士の国家試験の合格率は、
4年連続で100%
福本教授のもとで学ぶことの大きなメリットは、一般の作業療法プラスαの学びを得られること。高次脳機能に関する知識やスキルは、作業療法士として社会に出たときに大きな強みになるはずです。
「生きていくうえで一番大切なのは、誰もが自分らしく過ごせることだと思います。高次脳機能に関する知見をリハビリテーションに活かし、多くの患者さんたちに貢献することで、学生たちには世の中をより豊かにする一翼を担ってもらいたいですね」
また、他の大学と比較して、大和大学の保健医療学部は国家試験の合格率が高いのが特徴。例えば、作業療法士の国家試験の合格率は、直近4年連続で100%。その理由について、福本教授は次のように語ります。
「保健医療学部では、国家資格の試験対策に特化した授業カリキュラムを組んでいます。試験に関連するテーマを扱い、毎回、前回の授業の振り返りテストを実施。インプットとアウトプットを繰り返し行うことで、知識の定着を図ります。授業での学びが、ダイレクトに試験勉強につながるのがポイント。効率よく学べる環境を整えているので、授業に参加さえしていれば、着実に合格を狙えるようになるのです。学生たちにとって、国家資格の取得はゴールではなくスタート。スムーズに社会人としての一歩を踏み出せるよう、私たちは努力を惜しみません」


福本教授によると、作業療法のリハビリテーションと学生の育成は似ているといいます。いずれも感情を持った人間と向き合う仕事であり、感情に働きかけて本人のモチベーションを高めることが大切なのだそうです。
「高次脳機能にも関わっていますが、人は情動が喚起されるとヤル気が出ます。ほめられたときはもちろん、叱られたことがきっかけで『見返したい』という気持ちが湧くこともあるでしょう。また、ワクワクする体験は何年経っても記憶に残りやすい。だからこそ、叱咤激励を通じて学生たちの感情に働きかけ、『おもしろい』『もっと学びたい』と思ってもらえるような指導をすることが、私の役目だと言えるのです」




福本 倫之 教授
藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校(現:藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科)を卒業。作業療法士国家資格を取得し、愛媛県の病院へ就職。精神科で作業療法に携わる。その後、東京の病院で身体障害者の作業療法を経験。そこで高次機能障害と出会い、茨城県立医療大学大学院で学んで教員の道へ。2014年、開学と同時に大和大学へ。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME