
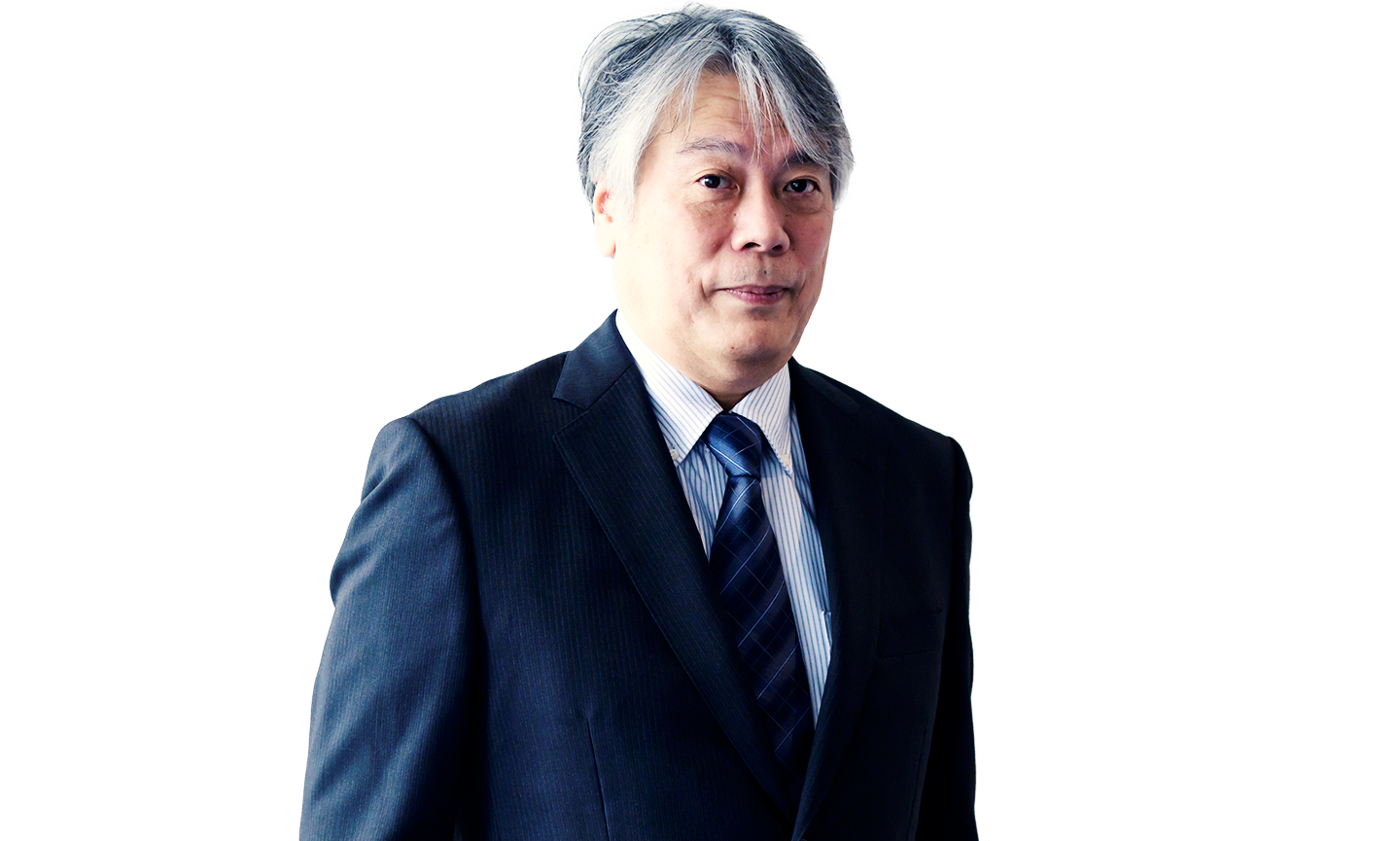
並列計算機の性能を最大限に引き上げ、
さまざまな社会課題の解決を目指す
並列計算機の性能を最大限に引き上げ、
さまざまな社会課題の解決を目指す
池田 孝利 教授


並列計算やアルゴリズムの最適化
などを通して、社会課題を解決する研究
池田教授は長年にわたって、複雑な処理を行う並列計算機の性能を最大限に引き出す研究を手がけてきました。特に、GPUというグラフィックス専用デバイスの可能性を追求。今ではAIやデータサイエンスの分野で必要不可欠とされている、GPUコンピューティングの普及に貢献しました。現在は、並列計算やアルゴリズムの最適化、高品質のソフトウェア開発やテスト手法の研究に注力。さまざまな社会課題を解決する一助になりたい、と考えています。
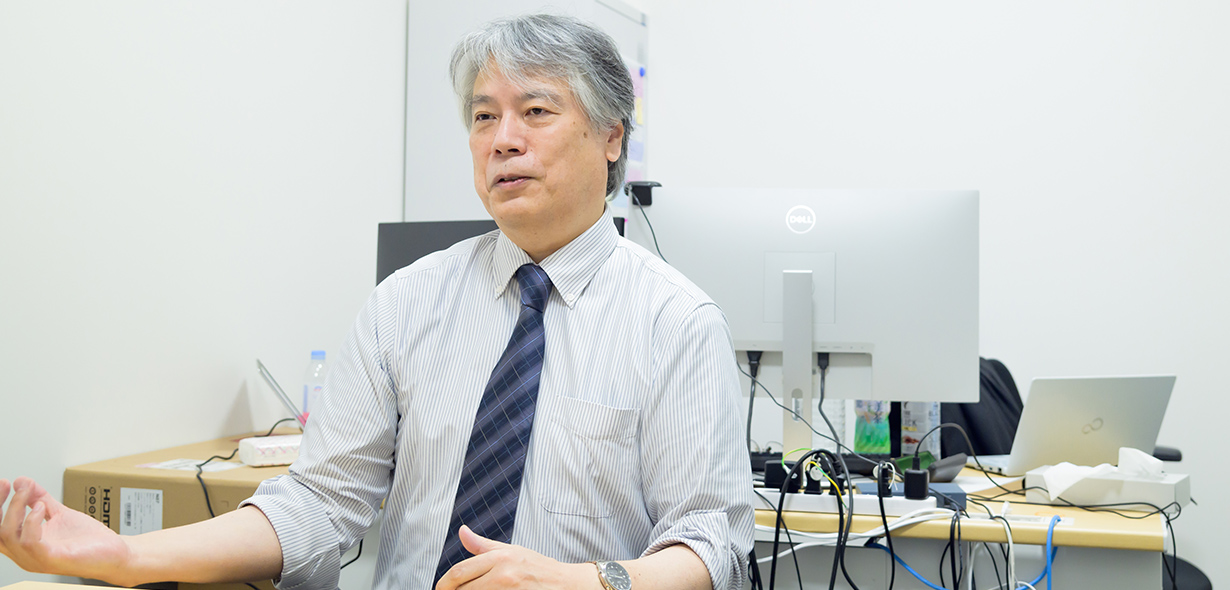
AIやデータサイエンスに欠かせない、
GPUコンピューティングの普及に貢献
コンピュータサイエンスのスペシャリストとして、複数の計算を同時に行う並列計算の技術や、より効率的に問題を解くためのアルゴリズムの最適化について研究を行っている池田教授。また、高品質のソフトウェアを開発する方法やテストする技術、さらに社会の問題を解決するためにシミュレーション技術を活用する研究にも取り組んでいます。
「主な研究テーマは、AIを活用した高速アルゴリズムや、量子コンピュータにヒントを得たアルゴリズムを開発すること。また、並列計算機の性能を最大限に引き出すことも、私のミッションだと言えるでしょう」
池田教授は、当時ゲーム機などに使われていたGPUという映像処理を専門とするデバイスを、一般のアプリケーションの高速化に利用する研究で大きな成果をあげた人物。AIやデータサイエンスの分野で欠かせない技術となっている、GPUコンピューティングの普及に大きく貢献しました。
「今から20年ほど前に大学院で博士号を取得したときの研究なのですが、映像処理専門のGPUを一般のアプリケーションの高速化に利用する取り組みは、当時は周囲からあまり理解されませんでした」


学会で研究成果を発表しても、ポジティブな反応は少なかったそう。ただ、GPUの可能性にいち早く着目していた池田教授は、めげずに研究に打ち込んできました。
「X線やCTスキャンで見たカラダの断面図をコンピュータで立体的に再現する“ボリュームレンダリング”という技術があるのですが、ある学生が、その計算を128台の計算機を用いて高速化し、学会で表彰を受けました。ボリュームレンダリングは、非常に大掛かりな設備が必要で、リアルタイムで計算できるものではありませんでした。私は、GPUを搭載したゲーム用のグラフィックボードひとつで、ボリュームレンダリングのリアルタイム描画を実現。研究室の指導教官に認めてもらったのです」


最新の計算技術を活用して、
さまざまな社会課題の解決に貢献
AIやデータサイエンスに欠かせない、GPUコンピューティングを世に広める一翼を担った池田教授。従来では考えられなかった速度や精度で課題を解決する技術を生み出せる点が、この研究のおもしろさだといいます。
「さまざまなアイデアを駆使してチャレンジする過程には、パズルを解くような楽しさがあります。また、計算技術は常に進化を続けているので、私のチャレンジにゴールはありません」
池田教授の研究の目的は、最新の計算技術を活用して社会課題を解決に導く方法を提供すること。シミュレーション技術を用いることで、複雑な問題を仮想的に再現し、その解決策を見出すサポートをしたいと考えています。
「特に、シェアリングエコノミーといった新しいビジネスモデルでは、資源を効率よく使い、公平に分配するためのシミュレーションを使って、社会への影響を調べることができます。また、男女平等を含むさまざまな社会問題に対して、どのように平等なチャンスを提供し、みんなが参加できる社会をつくれるかのヒントを導き出すことも可能。計算技術の進歩は、さまざまな分野で大きな変化をもたらします。最新の計算技術やシミュレーションを活用して、複雑な社会課題の解決策を提示することこそが、この研究の役割であると考えています」


また、IT技術が私たちの社会を支える一方で、ソフトウェアが老朽化、複雑化するという問題が発生しています。特に、長年使われてきたソフトウェアのメンテナンスは大きな課題。池田教授は、高品質のソフトウェアを開発する手法やテストの手法についても研究を行っています。
「長く使用され、技術的に古くなっているソフトウェアの新陳代謝をスムーズに行うことで、社会基盤となるシステムの信頼性を向上させることも、私の研究の目標のひとつです」


社会課題に対するシミュレーションの
重要性や実践的なアプローチを学べる
池田教授は、コンピュータが一般家庭に普及する前の1980年代から、主に機械学習やAIの分野で使用されるニューラルネットワークを、並列計算機でシミュレーションする研究に携わっていました。その頃、2024年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・ホップフィールド氏が来訪し、池田教授らの研究を視察。実際に並列計算機で動いているシミュレーションに興味を示し、並列計算機の前で、一緒に記念写真を撮ったそうです。このエピソードから、池田教授が早くから高度な研究に携わっていたことがわかるはず。そんな教授のもとで学べるのは、大きな魅力だと言えるでしょう。
「最先端のコンピュータサイエンスに触れ、社会課題に対するシミュレーションの重要性や実践的なアプローチを学べるのが特徴。実際の社会問題を仮想環境で再現し、解決策を導き出す過程を通して、問題解決に向けた実践的なスキルを身につけられるのもメリットです」
また、池田教授によると、大和大学ではコンピュータサイエンスや情報科学の理論的な知識だけでなく、データサイエンスや社会科学など、幅広い知見が得られる環境が整っているそうです。
「大和大学でなら、幅広い視点から実社会の課題に取り組む力を養うことができるでしょう。多角的な視野を持って実践的な研究に取り組むことで、学術的な知識を社会に役立てる能力を育むことができると思います」


池田教授のもとで最先端の研究に携わり、大和大学で視野を広げることで、これからの技術進歩や社会の発展に大きな影響を与える人材へと成長していけるはず。最後に、教授から見た理想的な学生像について教えてもらいました。
「好奇心やチャレンジ精神が旺盛な方です。私自身、誰もできないことに挑めることを原動力に、これまで研究を続けてきました。新しいことに挑戦する際は、目の前に大きな壁が立ちはだかります。けれども、それを乗り越えたときには、これまで見たことがない景色が広がっているでしょう」

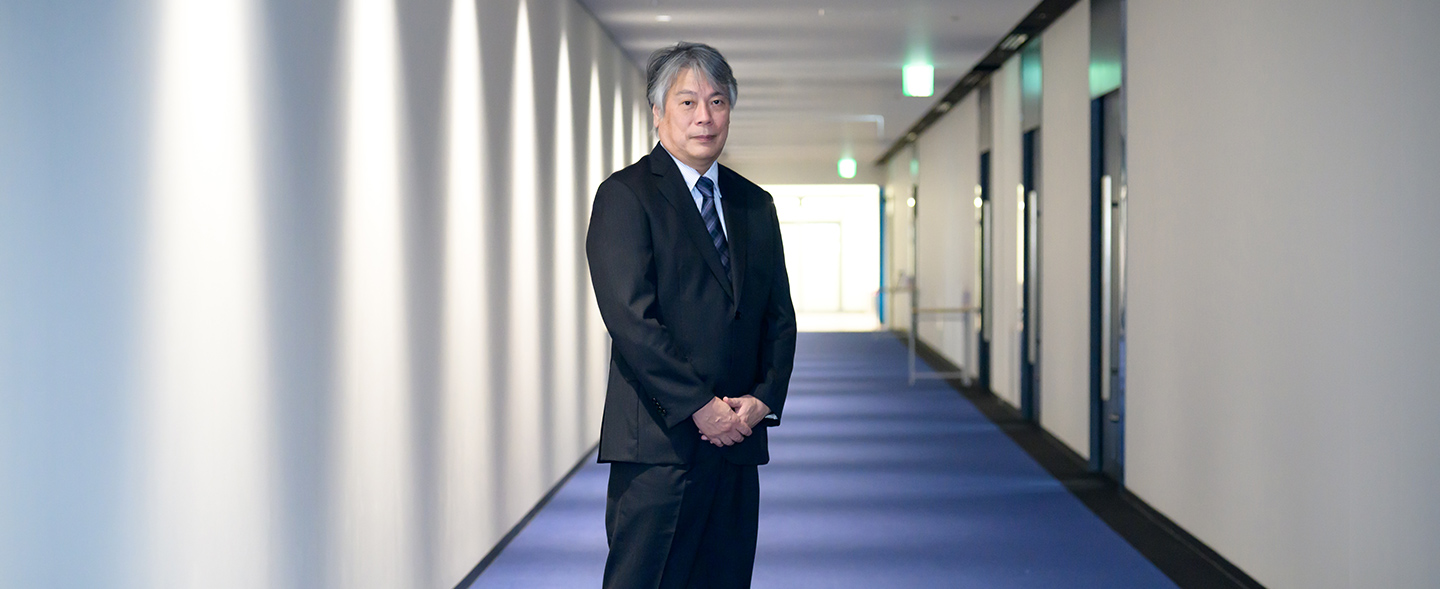


池田 孝利 教授
大阪大学大学院情報科学研究科で、博士号を取得。この時期に、GPUを一般のアプリケーションの高速化に利用する取り組みで大きな成果を残す。その後、慶應義塾大学経済学部や京都大学大学院経営管理教育部で学んだ後、大和大学情報学部の教授に就任する。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME