

“トラウマの癒し”というテーマを軸に、
世界平和の実現を目指す
“トラウマの癒し”というテーマを軸に、
世界平和の実現を目指す
青地・イザンベール 真美 准教授


ヴェトナム帰還兵や人身売買の被害者などの
心の傷と平和についての研究
「トラウマの癒しによる平和への貢献」というテーマを掲げ、青地・イザンベール准教授は、ヴェトナム戦争でアメリカ兵が引き起こした加害者トラウマや、ネパールの人身売買の被害者のトラウマなどについて研究を行っています。人々が経験する心の痛みや悲しみを共有し、憎しみを赦しに変える営みが、世界平和への貢献につながるはず。そういった強い信念を持ち、日々研究活動に取り組んでいます。

一生十字架を背負い、辛い記憶を思い出して、
語り続けることが加害者の使命
2016年4月、ジョン・ケリー氏が米国務長官として初めて、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花をしました。同時に、公園内の広島平和記念資料館も見学。展示内容について、「胸をえぐられるよう」とコメントしました。青地・イザンベール准教授は、ケリー氏が広島に寄せる想いの原点は、自身の戦争体験にあるのではないかと分析しています。
「ケリー氏は、実はヴェトナム戦争の帰還兵です。1969年のゲリラ掃討作戦で残忍行為を行い、『その事実を誰にも言えず、自殺を考えたこともあるなど、悪夢の32年間を過ごしてきた』と、2001年に胸の内を明かしています。戦争から帰ってきてからは、反戦運動に参加。1971年には、他の退役軍人とともに、抗議の意を表すために連邦議会議事堂の建物に勲章を投げつけて国家に返す、というデモンストレーションを行いました」
青地・イザンベール准教授は、過去に発表した論文『ヴェトナム帰還兵のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の形成--トラウマと兵役をめぐる言説』のなかで、「ヴェトナム人にとっては加害者である兵士が、アメリカという国家に対しては被害者であった」という仮説を提示しています。
「アメリカ兵はヴェトナム戦争で数々の残虐行為を行いましたが、最前線で闘っている若者たちは命令を拒否することができません。そうして行った数々の行動がトラウマとなり、精神的問題を抱えるヴェトナム帰還兵が後を絶ちませんでした。トラウマ体験の精神的後遺症を表す言葉として広く知られているPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、実はヴェトナム帰還兵の多くに精神障害が見られたことから研究がスタートしたのです」


歴史の証言者として、戦争などの被害者にスポットライトが当たることがよくあります。思い出したくもない過去の体験を語るのは、精神的に非常に辛いもの。ですから、青地・イザンベール准教授は「被害者は無理に語る必要はない」と考えているそうです。
「その代わりに、加害者が歴史の証言者になるべき。自身が行った残忍行為を思い出して語るのは、もちろん精神的に大きな負担になるでしょう。それでも、一生十字架を背負いながら、何度でも辛い記憶を思い出し、語り続ける。それこそが、加害者の使命であると私は考えています」


自由に自己表現できる“さをり織り”には
メンタル・ヒーリング効果がある
ケリー氏をはじめとするヴェトナム帰還兵の話からもわかるように、青地・イザンベール准教授は「心の傷と、外交や戦争と平和」をテーマに研究を行っています。
「オバマ大統領の広島訪問を可能にした当時のケリー国務長官のように、ヴェトナム戦争で残虐行為を犯し、赦しを求める帰還兵たちが、どう平和に貢献できるのかに注目しています」
また、青地・イザンベール准教授は、被害者の心の傷にも目を向けています。機織りの一般的なルールに縛られず、自分の感じるままに織る“さをり織り”を通して、ネパールの人身売買被害者のサポートを行いました。
「心を無にしてひたすら目の前の織物に集中できる“さをり織り”には、トラウマを忘れさせる効果があります。“さをり織り”による国際支援を通じて、歴史の証人である被害者が人身売買について語ることが、被害者の幸せに寄与するかどうかを研究。ただ、途中から被害者の女の子たちとは、音信不通になりました。きっと“さをり織り”を必要としなくなり、一人の平凡な女性として社会に溶け込んでいるのでしょう。私は被害者が歴史の証人になる必要はないというスタンスなので、むしろそれでよかったと思っています」


“さをり織り”は、2004年のスマトラ沖大地震・インド洋大津波や、2011年の東日本大震災の被災者を支援するためにも導入されたそうです。
「岩手県三陸地方の仮設住宅で“さをり織り”を始めた女性たちに調査を行った結果、一定のメンタル・ヒーリング効果が見てとれました。また、“さをり織り”は被災者自身が自主的に行うアート。『支援してもらう側』という立場ではないので、プライドを持って芸術活動を行えるのも特徴です」
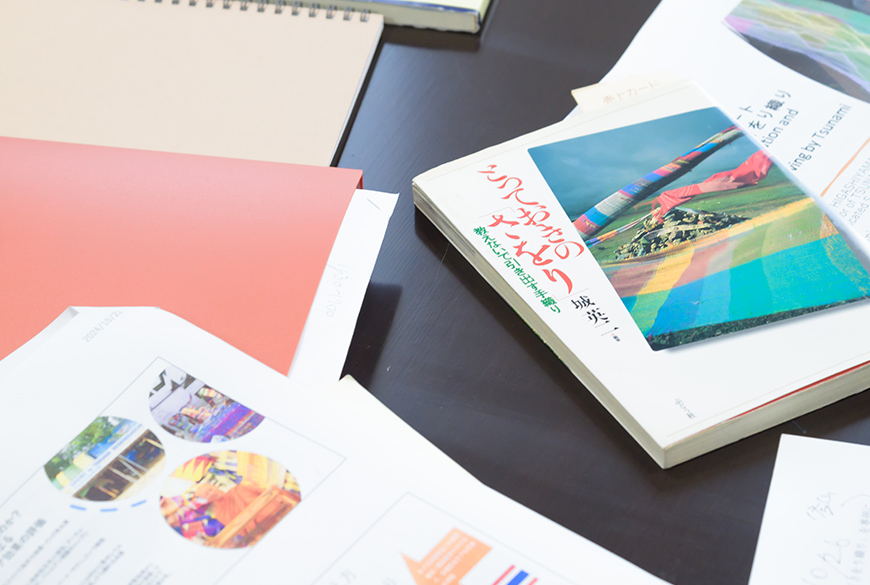

心の傷を共有し、憎しみを許しに
変えることが、世界平和への第一歩
ヴェトナム帰還兵や人身売買被害者など、心に大きな傷を負った人々をテーマに、さまざまな研究に取り組んでいる青地・イザンベール准教授。この研究には、どのような意味があるのでしょう。
「『トラウマを癒すことが世界平和につながる』というテーマは、グローバルなコミュニケーションが発展した現代だからこそ力を発揮すると考えています。私たち一人ひとりが経験する心の痛みや悲しみを共有し、憎しみを赦しに変える努力をすることで、世界平和の実現に近づけるでしょう」
青地・イザンベール准教授が扱っているのは、非常に重たい研究テーマ。トラウマと平和に関する研究内容を学生にどのように紹介すれば効果的か、今は試行錯誤を重ねているところだそうです。
「ただ、権力は持つことが目的ではなく、それを使わないために学ぶものです。法律も同様に、使う必要がないように学び、使われないようにするために学ぶもの。このような政治学の基本を、ぜひ人生に役立ててもらいたいと思っています」


青地・イザンベール准教授は、有名ブランドのモデルや通訳を経験するなど、これまでに学術以外の分野でも幅広く活躍してきました。専業主婦として子育てに専念していた時期もあり、とても人生経験が豊かです。
「社会人になれば人生の多くの時間を、仕事(家事・育児も含む)に費やすことになるでしょう。ですから、学生たちには『心から愛せる仕事』を見つけて、幸せな人生を過ごしてもらいたいです。そのためにも、大学時代に多くのことを吸収し、幅広い教養を身につけてください」




青地・イザンベール 真美 准教授
上智大学法律学部国際関係法律学科卒業。その後、さまざまな経験を経て、1997年に東京大学国際社会科学で国際関係論を学ぶ。1998年からは、国際政治学のプロとして東海大学の非常勤講師に。現在は、大和大学政治経済学部の准教授として活躍している。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME