

クレジットカードによる非接触取引を
さらに普及させることがミッション
クレジットカードによる非接触取引を
さらに普及させることがミッション
髙尾みどり准教授


イノベーションの普及や
イノベーション・マーケティングについて
イノベーションの普及について研究を行っている髙尾准教授。なかでも、キャッシュレス決済に注目しており、コロナ禍以降は主要先進国から出遅れている日本のキャッシュレス決済の利用を促進すべく、「クレジットカードの非接触取引の普及の課題と対策」について研究しています。また、イノベーション・マーケティングにも注目。イノベーションに成功した商品を題材に、そのマーケティング手法について分析する授業を行っています。

他の主要先進国と比べて、
キャッシュレス決済の普及率が低い日本
イノベーションの普及をテーマに、ユニークな研究を行っている髙尾准教授。近年は、コロナ禍におけるキャッシュレス決済について、データ分析をもとに読み解く研究を進めてきました。
「2020年に新型コロナウイルス感染症が蔓延し始めてから、世の中的にキャッシュレス決済に注目が集まりました。ただ、当時の主要先進国のキャッシュレス決済の普及率が40~60%台であるのに対して、日本はわずか29.8%と3割にも届かなかったのです。そこで、2020年時点で63.9%をマークしていたイギリスと日本の違いを比較。すると、あちこちにATMがある日本と比べてイギリスは現金がおろしにくい、イギリスは日本よりも端末の導入コストを安く抑えることができて手数料も低い、などの違いがあることがわかりました」
キャッシュレス決済には、クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード決済など、さまざまな種類があります。そのなかで、もっとも取扱高が高いのはクレジットカード。日本におけるキャッシュレス決済のうち、約9割を占めているのです。にもかかわらず、日本政府はコロナ禍において電子決済の利用を呼びかけるにとどまりました。いっぽうイギリス政府は、ICチップが搭載されたカードを端末にタッチするだけで決済が完了する、非接触によるカード決済の利用を呼びかけていたのです。
「2020年時点で非接触化が8割を超えていたイギリスにとって、キャッシュレス決済は新型コロナウイルス感染症対策として有効だったと言えるでしょう。一方、非接触化が遅れていた日本において、クレジットカード決済は人とモノとの接触が多く、コロナ禍において必ずしも安全な取引とは言えなかったのです」


ただ、髙尾准教授が新聞記事のデータをもとにした分析によると、コロナ禍に突入してから感染リスクを避けるために、日本における“非接触化のニーズ”が高まってきたことがわかったのだとか。
「キャッシュレス決済比率が高く、非接触化も進んでいるイギリスは模範的な存在です。2022年に発表した論文では、コロナ禍でのより安全なキャッシュレス決済の実現に向けて、日本はイギリスを参考に非接触化を推進すべきであるという結論を導き出しました」


クレジットカードの非接触取引は
“導入”から“利用”のフェーズへ
髙尾准教授は、2023年に『クレジットカード非接触取引普及の課題と対策』という論文を発表。その過程でクレジットカードの非接触取引の状況についてリサーチを行ったところ、日本における非接触型クレジットカードの発行枚数は堅調に推移していることがわかったそうです。
「Visaカードに限った話ですが、新規会員のカード発行時や既存会員のカード更改時に、非接触型クレジットカードの発行をスタートしました。すると、2019年6月時点では1,000万枚だったのが、2023年5月には1億枚を突破したのです」
また、全国各地の公共交通機関をはじめ、非接触型のクレジットカードが利用できる場所も増えてきているのだとか。例えば、関西国際空港から大阪市内などに向かう際に多くの人が利用する南海電鉄では、2022年12月に非接触型クレジットカードのタッチ決済を導入。交通系ICカードではなく、クレジットカードを改札にかざすだけで電車に乗れるとあって、外国人観光客の利便性が大きく向上しました。
「ここ数年で、非接触型クレジットカードによる取引はかなり普及したと言えるでしょう。実際、新聞記事のデータをもとにした分析からも、クレジットカードの非接触取引が“導入”から“利用”のフェーズへと移行しているのが見て取れました」


ただ、髙尾准教授によると、非接触型クレジットカードの普及拡大を目指すには、まだまだ多くの課題が残っているといいます。
「キーワードは“認知度アップ”“利得性の提供”“高齢者への普及”“地方での導入”“大学研究機関の関与”の5つ。これらの課題を複合的に解決できる方法は、交通機関での非接触型クレジットカードのタッチ決済導入だと考えています。また、かつて経済産業省が実施したポイント還元事業のように、消費者にとってメリットを実感できるキャンペーン施策を国が支援することで、さらなる普及が期待できるでしょう」


イノベーションに成功した
商品のマーケティング手法を分析する授業
キャッシュレス決済に関する研究のほか、イノベーション・マーケティングについても研究を行っている髙尾准教授は、人々の暮らしに身近な商品を活用した授業を展開しています。具体的には、イノベーションに成功した商品を題材に、画期的な新商品のマーケティング手法を分析していくというものです。
「例えば、“ペットボトル入りのコーヒー”“ルゥでもレトルトでもない第3のカレー”など、新たなジャンルを切り開くことになったヒット商品の開発やマーケティングの舞台裏について紹介。生活に身近な商品なので興味を持ちやすく、楽しく学べるようで、学生たちからも好評です」
髙尾准教授の授業では、「流通を通さない直販で成功しているビジネスは?」「高額でも絶対に売れるモノは?」「まだ世の中に存在していないけどヒットしそうな商品は?」など、さまざまなテーマでグループワークも実施しています。
「学生たちの自由な発想や柔軟なアイデアに、驚かされてばかりです。直販で成功しているビジネスとして、『電気・ガス・水道などのインフラ事業』といった声があがったときには、思わず目からウロコが落ちました」


髙尾准教授によると、単に知識をインプットするだけでなく、自分たちで考えてアウトプットするということが大事なのだとか。
「そうすることで、学生たちは受け身ではなく主体的に授業に取り組むことができます。また、他の人の意見に耳を傾けることで、新しい視点や価値観に触れることもできる。グループワークを通して、大きな刺激を得られるでしょう。こうした授業を受けることで、学生たちが少しでもマーケティングを身近に感じ、おもしろそうだと興味を持ってくれれば、すべての苦労が吹き飛んでしまいます」



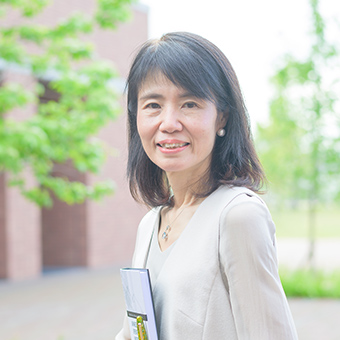
髙尾みどり 准教授
同志社大学経済学部卒業後、大手カード会社に就職。商品・サービスの企画開発や情報セキュリティ管理などに携わる。在職中に筑波大学大学院ビジネス科学研究科、東京大学工学系研究科で学び、東京大学未来ビジョン研究センターの客員研究員となる。2024年、大和大学へ。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME