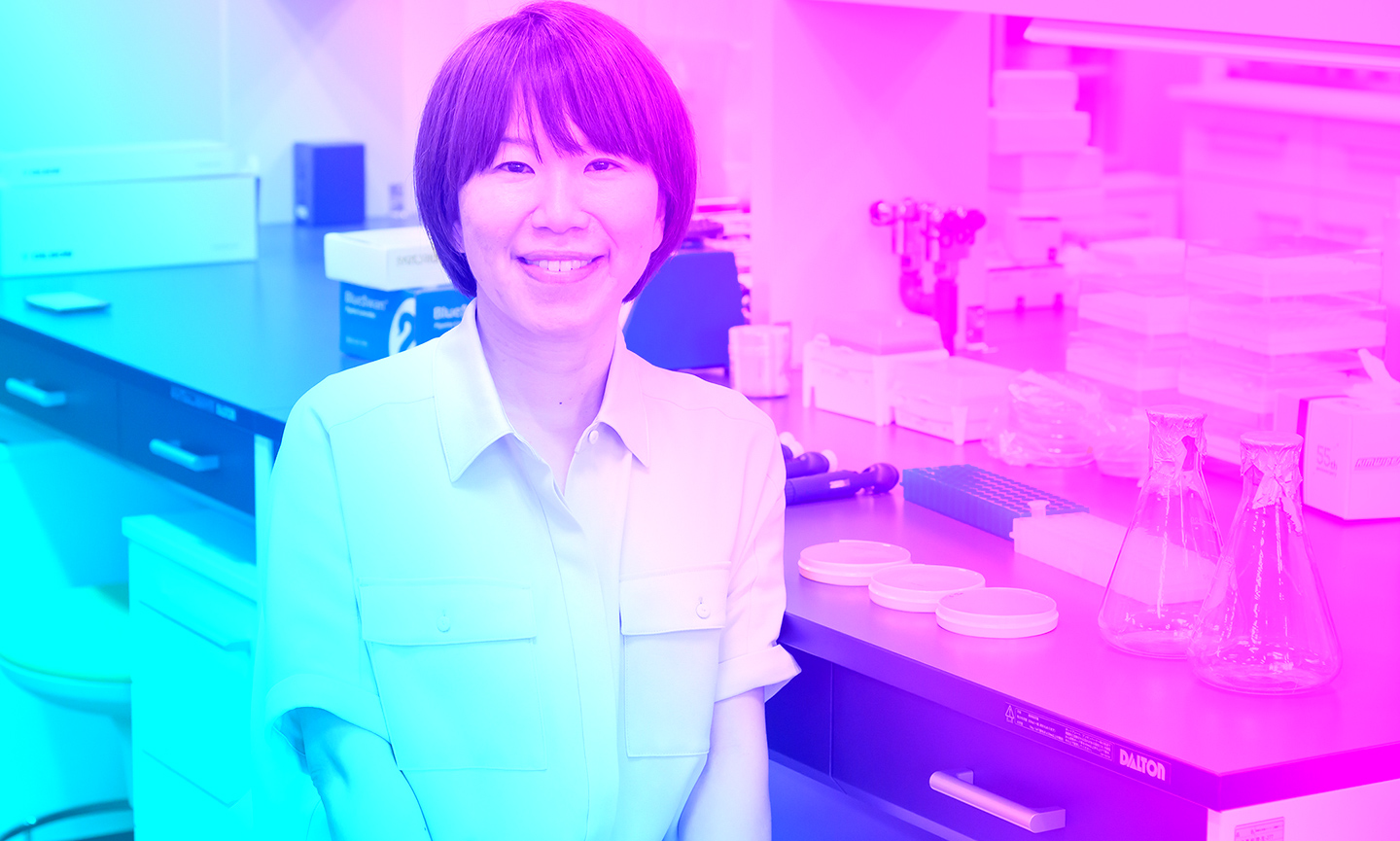

持続可能な社会づくりにつながる、
微生物の新たな可能性を引き出す
持続可能な社会づくりにつながる、
微生物の新たな可能性を引き出す
中瀬 由起子教授


高温にも負けない酵母と
香辛料が切り開く発酵の未来
生物の力を最大限に引き出し、持続可能な社会づくりに貢献することを目的とし、微生物の中でも特に酵母を用いた基礎研究に取り組んでいる中瀬教授。これまでの生育限界を超えて高温でも生育可能となる酵母の新たな可能性と、香辛料の成分による発酵促進という、2つの大きな発見を行い、現在はそれらのメカニズムの解明に注力しています。気候変動に強い発酵技術の開発や、発酵を活用した持続可能な食料・エネルギー生産につながる、注目の研究だと言えるでしょう。
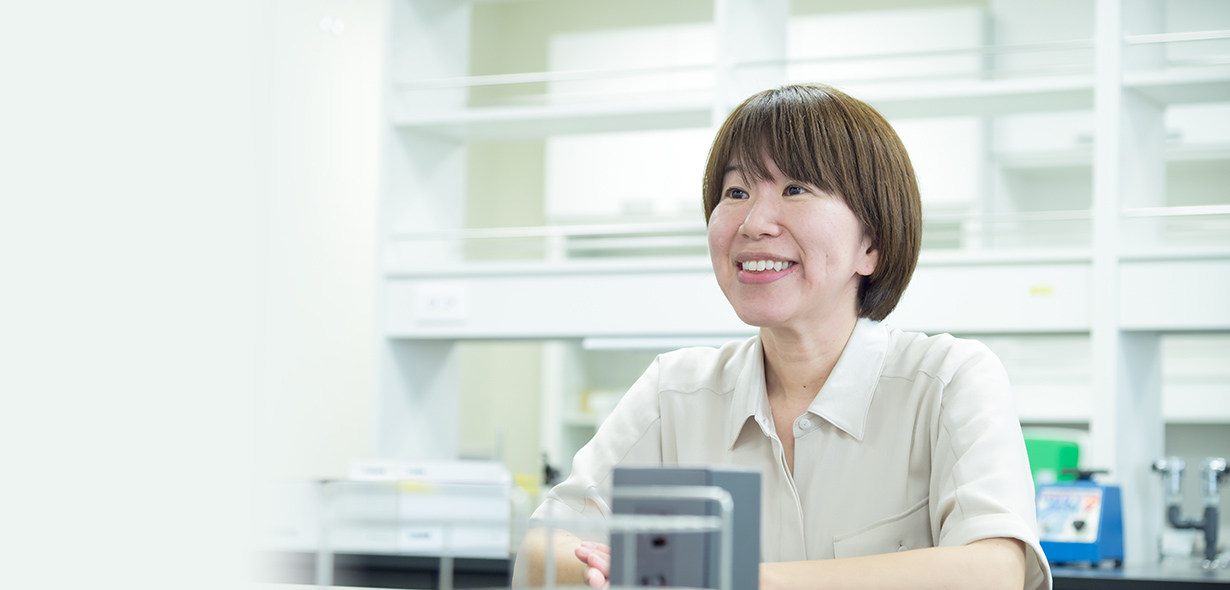
高温に強い酵母や農作物の開発に
つながる大きな発見!
食品の製造や医薬品の開発、環境保全など、私たちの生活に身近なところで活躍している微生物。なかでも酵母は、パンや味噌などの発酵食品、日本酒やビールといった飲料づくりに欠かせない存在として知られています。長年酵母の研究に取り組んできた中瀬教授は、酵母の生命力に関わる大きな発見をしました。
「私が注目しているのは、細胞の成長やエネルギー代謝を制御する『TORC1経路』という細胞内のセンサーのようなシグナル伝達経路。TORC1は細胞の成長や代謝を調節するだけでなく、がんや糖尿病などの疾患にも深く関与する分子として、医学の分野でも注目されています。私は『TORC1経路』が、酵母の高温耐性にも関わっていることを発見しました」
生物にはそれぞれ特定の生育温度帯があり、その上限温度を超えると顕著な生育障害が起こります。酵母の生育上限温度は37度付近で、それ以上では生育できません。しかし、中瀬教授らのグループは、TORC1阻害剤として知られるラパマイシンを加えることで、酵母が高温でも生存できることを明らかにしたのです。
「生物が生育上限温度を超える環境で生きられない主な理由は、タンパク質が熱によって変性してしまうからだと長く考えられてきました。けれど実は、高温の環境下では『TORC1経路』が細胞の成長を抑えるブレーキのような役割を果たしていることがわかってきたんです。そこで、ラパマイシンによってそのブレーキを解除すれば、高温環境でも元気に生きられるのではないかと考えました」

出芽酵母(左)と分裂酵母(右)

現在、そのメカニズムの解明を進めているという中瀬教授。この研究は学会で賞を受賞するなど、大きな注目を集めています。
「この研究を通じて、気候変動や工業発酵における高温ストレスに負けない、丈夫な耐熱性酵母を開発したいと考えています。それにより、発酵の安定化や生産効率の向上が期待でき、気温変動による工業生産への悪影響も抑えられるはずです。さらに、この耐熱性の仕組みは酵母だけでなく植物にも応用できる可能性があります。地球温暖化で農作物の生育環境がますます厳しくなるなか、暑さに強い作物の開発にもつなげることもできるでしょう」


再生可能エネルギーの普及にもつながる、
発酵効率を高める研究!
中瀬教授は、酵母の高温耐性の研究に加え、発酵効率を高める新しい方法の開発にも力を入れています。特に注目しているのが、香辛料のウコンに含まれる成分のクルクミン。ウコンはカレーなどの香辛料として古くから用いられ、防腐や殺菌作用が知られています。発酵促進と結びつけて考えられることは、これまでありませんでした。
「香辛料は本来、食品の保存に役立つ殺菌や防腐の効果があるとされてきました。しかし、ウコンに含まれるクルクミンを酵母に加えることで発酵が活発になり、発酵効率が高まることを発見したのです」
この発見をもとに、「アルコール発酵方法および発酵促進剤」の特許申請を行ったという中瀬教授。昨年夏、『大学見本市~イノベーション・ジャパン』で研究成果を発表したところ、食品メーカーやエネルギー関連企業からも関心が寄せられ、商品化を望む声も上がっているそうです。
「今は、クルクミンを加えると発酵が進むメカニズムの解明に取り組んでいるところです。もし解明できれば、発酵食品やアルコール飲料の製造コストの削減や工程の改良、新しい製品の開発にもつながるはず。そう考えると、この発見はとても大きな意味を持っていると言えるでしょう」


さらに、クルクミンを加えると発酵が進むメカニズムの解明は、近年注目されているバイオエタノールの分野にも応用できるそうです。バイオエタノールは、トウモロコシやサトウキビなど、植物由来の糖を酵母が発酵させてつくる再生可能なクリーン燃料。環境にやさしいエネルギーとして、将来性が期待されています。
「クルクミンによる発酵促進の仕組みが明らかになれば、バイオエタノールの効率的な生産が可能になり、環境にやさしいエネルギーの普及にもつながるでしょう。この研究は、食料生産の分野にとどまらず、持続可能な社会の実現にも大きく貢献できる、非常にホットなテーマなのです。」


大和大学オリジナルの
クラフトビールづくりにも挑戦!?
酵母の高温環境への適応力強化と発酵効率の改善という2つのアプローチを通じて、気候変動に強い産業技術の確立と、持続可能な食料・エネルギー生産への貢献を目指している中瀬教授。研究のおもしろさは、従来の常識を覆す発見ができることにあるといいます。
「『TORC1経路』はこれまで細胞の成長を促すものだと考えられてきましたが、高温下では成長を抑える役割も持つことを明らかにしました。細胞が環境ストレスに適応するために成長を抑える仕組みは非常にユニークで、耐熱性の向上に役立つと考えています。また、香辛料のウコン由来の成分であるクルクミンが、酵母のストレス耐性を高め、発酵効率を大幅に向上させることも偶然発見しました。基礎研究は思い通りにいかないことがほとんどですが、こうした発見に出会えると、それまでの苦労は吹き飛んでしまいます」
また、『TORC1経路』はインスリンなどの働きにも関わる分子で、医療分野でも盛んに研究されています。さらに、ラパマイシンは抗がん剤としても使われているもの。酵母の高温耐性の研究は、将来的には生命科学や医療分野にも応用できる可能性を秘めていると言えるでしょう。
「私たちが取り組んでいるのは基礎研究なので、実用化にはまだまだ時間がかかります。特に創薬は複雑で、成果を社会に還元するまでには長い道のりが必要。けれども、熱ストレスを緩和する薬の開発に役立てることができれば、これほどうれしいことはありません」


そのほか、中瀬教授は近い将来の目標として、大和大学のキャンパスで採取した野生酵母を使い、オリジナルのクラフトビールを開発することを掲げています。
「野花や果実の表面に付着している野生酵母を学生と一緒に採取し、発酵力の強い酵母を見つけて、それを使ったお酒を造り、商品化したいと考えています。地域の資源を活かしたブランドを創出し、微生物の多様性や発酵技術の魅力を多くの人に伝えていきたい。さらには、微生物の多様性と発酵技術の魅力を広く伝えるプロジェクトを通して、地域活性化にもつなげていきたいと考えています」



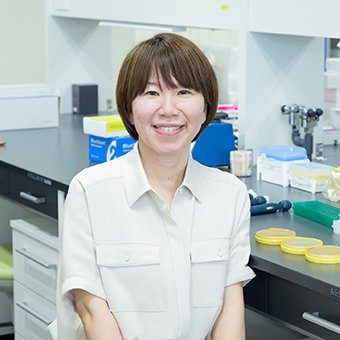
中瀬 由起子 教授
大阪市立大学大学院理学研究科で博士号を取得。その後、京都大学放射線生物研究センターの研究員などを経て、現在は奈良先端科学技術大学院大学の客員教授をしながら、大和大学の教授として活躍している。







 アクセス
アクセス 資料請求/問合せ
資料請求/問合せ




 HOME
HOME